
肩こりの原因、チェック方法、治し方、改善トレーニングを解説
若い人から高齢者まで、幅広い世代を悩ませる肩こりを改善するには、原因や対策を知ることが重要です。 マッサージを施すことで一時的に肩こりが解消されたとしても、根本の原因に対処しなければすぐに痛みや違和感が現れます。 慢性的な肩こりは肩の痛みだけでなく、頭痛やめまいといった症状に繋がる可能性もあります。 また、肩こりの直接的な原因が肩以外の部位にある場合、肩のマッサージや痛み止めの薬を飲んでも改善に繋がらないケースが存在します。 肩こりを放置することなく、原因や直し方、改善のためのトレーニングについて学んでいきましょう。
関連記事
肩こりにおすすめの枕人気おすすめ10選!【いびき・頭痛・腰痛にも】
肩こりのチェック方法

肩こりの対処方法や原因を学ぶ前に自分の肩こりがどれだけ重大なのかチェックすることをおすすめします。肩こりをチェックする際の目安となるのが特定の姿勢を取ったときに腕が上がる高さです。
まずは、足を揃えてまっすぐ立った状態から腕を前に伸ばしましょう。そこから肘を手前に曲げて、前腕と二の腕の角度を90度にしてください。両腕を90度に曲げたら、今度はその状態で肘同士をくっつけます。
この基本姿勢から肘同士を離すことなく、まっすぐ上に腕を引き上げてください。肩こりが重症な人は、胸よりも高い位置まで肘が上がることはありません。 顎まで上げられない人は、比較的重度の肩こりといえます。
唇の高さに肘が来る場合は肩こりの症状が軽く、改善しやすい状態です。肩こりの心配がほとんどない人は、鼻の位置まで両肘が持ち上がります。
肩こりのメカニズム。肩こりはなぜ起きるのか

肩こりの原因は多々ありますが、肩こりのほとんどは肩周辺の筋肉が血行不良に陥るというメカニズムによって成り立っています。血行とは血液の流れであり、私たちの血液は栄養や酸素を運ぶ重要な役目を果たしているのは皆さんも知っている通りです。
何らかの原因で血行不良に陥ることで筋肉中にうっ血が発生し、不快感や痛み、筋肉の緊張といった現象を引き起こします。血行不良の筋肉には老廃物が蓄積し、蓄積した老廃物によって血管が圧迫されることが肩こりの痛みの一因といわれています。
肩をマッサージすることで一時的に肩こりが楽になるのは、外からの圧力によって血行不良が改善されるからです。ただし根本の原因を取り除かない限り、肩周辺の筋肉の血行が滞り、肩こりが再発することになります。
肩こりの原因

肩こりが発生する原因としては以下に挙げる事柄が考えられます。
同じ姿勢を長時間継続する
肩こりが発生する原因の中でもデスクワーカーや学生といった机に向かうことが多い人に見られるのが、長時間同じ姿勢を継続することです。机に座って作業をするとき、多くの人は首を前に突き出す姿勢になります。
実際にこの体勢になってみると、肩周辺の筋肉が縮まっているのがわかることでしょう。肩の筋肉を縮ませた状態を継続することで血行が悪化し、慢性的な肩こりを引き起こすケースが後を絶ちません。
眼精疲労
前のめりな姿勢で仕事をして目の前のパソコンを見続けてしまうと、毛様体筋という目の筋肉が緊張した状態が続き、目に大きな負担がかかります。
これは目には遠くを見ると毛様体筋の緊張がゆるみ、逆に、近くを見ると緊張するという特徴があるからです。
そして、目に大きな負担がかかり、目が疲れる・ぼやける・かすむ・しょぼしょぼするという症状が現れると眼精疲労という病気の恐れがあると言えます。
眼精疲労により視界がぼやけてくると、パソコンの画面をより見ようとするため、目とパソコンの距離が近くなる=顔を前に突き出すような形になります。そのような態勢ですと首に負担がかかり、最終的に肩に負担がかかって肩こりの原因にもつながるのです。
運動不足
肩こりの中でも、身体を動かす機会が少ない人に多く見られるのが運動不足です。肩こりの原因が肩周辺の筋肉の血行不良にあることはお伝えした通りです。
私たちの血管は身体を動かすことで血液の循環を促すことができます。しかし運動する習慣がない人は運動による血行促進効果を得られないため、日常的に運動をする人よりも血行不良に陥りやすい傾向にあります。
運動不足の人は肩回りの筋肉が強張りやすく、肩こりに悩まされやすいことを自覚しておきましょう。
冷え性
女性だけでなく、冷房の効いた部屋で仕事をする男性の肩こりの原因としても近年注目されているのが冷え性です。冷え性の人は指などの末端部分はもちろんのこと、内臓をはじめとした身体の内側まで冷えているケースが多く見受けられます。
身体の内側が冷えているということは血管も冷たくなっており、硬くなった血管は柔軟性が低下し、筋肉の末端まで血液を送ることが困難になるため、肩回りの筋肉を強張らせて肩こりを引き起こすのです。
ストレス
ストレスは多くの不調の原因であり、肩こりを引き起こす要因としても知られています。ストレスを感じた身体は交感神経が優位に働き、筋肉が緊張しやすくなります。
強い緊張状態が長く続くと筋肉は強張りやすく、血行不良に陥る確率が高いのです。
肩こりがひどくなると吐き気を伴うことも

皆さんは、もし肩こりがひどくなってしまった場合に、吐き気を伴うこともあることをご存知でしょうか?
まず、そもそも肩こりというのは、肩回りの筋肉がこわばり、緊張状態にあるがゆえに、生じるものです。
肩回りの筋肉の緊張は、頭や首の緊張にもつながり、さらに悪化すると、自律神経の乱れや、血行不良を原因とした代謝の悪化へとつながります。
そして、最終的にその自律神経の乱れが、吐き気を催すことにつながってしまうのです。
>>肩こりがひどくなると吐き気やめまいを催すことも。その原因とは?
緊張型頭痛とは?

緊張型頭痛とは頭や首回り、そして背中や肩回りの筋肉が緊張することを原因として起きる頭痛のことです。
頭痛に悩まされている日本人の中で、最も多いのがこの緊張型頭痛と言われています。
その数は、なんと15歳以上の人では、2割もの人が緊張型頭痛に悩んでいるとされています。
緊張型頭痛は、長い時間にわたって同じ姿勢をとり続けることや姿勢の悪さ、自分に合っていない枕を使い続けることや運動不足など、さまざまなことが原因として挙げられていますが、最も多いのはストレスです。
ストレスにより頭や首周辺の筋肉がこわばり緊張した結果として生じます。
そして、緊張型頭痛に悩まされている人は、首や肩こりを伴っていることが多くあります。
肩こりの改善・解消方法

肩こりを改善するには自分の肩こりの原因が何かを見極めたうえで、原因に対応した方法を実践する必要があります。
ストレッチやマッサージ
同じ姿勢の継続や運動不足が原因で肩こりに悩んでいる人は適度な運動を日常生活に取り入れてみましょう。肩こりに陥った肩周囲の筋肉の血行を促進するには、運動によって刺激を与えるのが効果的です。
血行促進という点に注目すると、ランニングや水泳といった有酸素運動がおすすめです。
有酸素運動とは運動の最中に多量の酸素を体内に取り入れるトレーニングであり、血行促進に効果があるといわれています。
ただし、有酸素運動は長い時間を連続して運動する必要があるため、まとまった時間を確保する必要があります。忙しい現代人はまとまった時間の確保が難しい方が多いでしょう。
そのため、肩こりを解消する方法の一つとしてストレッチやマッサージで血行を促進するのが良いでしょう。
ストレッチポールなどのグッズを用いるストレッチは自宅でも簡単に行えますし、マッサージであれば仕事の休憩中に肩の筋肉の強張りを和らげることができます。
>>肩こりの簡単ストレッチを紹介|肩こりのチェック方法も合わせて解説!
>>肩こりに効果的なマッサージとツボ押しを紹介|プロが教える肩こりセルフケア
姿勢を改善する
デスクワーカーや学生など、長時間机に向かうことが多い人の中には、肩こりの原因である同じ姿勢の継続が避けられないこともあるでしょう。本来であれば適宜休憩を取り、身体をほぐす運動を取り入れることが肩こりを解消する際の理想です。
休憩を取るのが難しい場合には、普段から肩こりになりにくい姿勢を習得しましょう。
肩こりになりやすい姿勢は、両肩が胸の方に寄ってしまった状態です。 机の上に手を置いて作業をしたり、キーボードを打ったりといった場面では肩が縮こまった姿勢になりやすいですよね。
そこで意識していただきたいのが、肩甲骨の可動性とポジションです。
肩甲骨は背中側に位置する肩周りの大きな骨のことで、肩甲骨同士の間を適度に寄せる(背骨に寄せる)ような姿勢でいることが、肩甲骨のポジション・姿勢の乱れを修正し、肩こりを予防することに繋がります。
強張った胸の筋肉も自然に引き延ばされますから、肩こりに悩んでいる人がこの姿勢を続けることで、肩こり改善のきっかけにもなるでしょう。
肩甲骨の可動性とポジションを意識して、肩こりに悩みにくい姿勢を習得してください。
リラックスタイムを設ける
ストレスによる肩こりを解消するには、心身ともに安らげる時間を確保することが大切です。
お風呂にゆっくり浸かる、好きな音楽に没頭するなど、仕事や人間関係の悩みから自分を解放してあげてください。
ストレスの項目でもあったように、副交感神経が優位な状態にすることで、筋肉の緊張がほぐれた状態になり、血流が増進し、肩こり解消につながります。
肩こりに効くマッサージ・ストレッチ
肩こりを解消するには、上記の原因に対処すると同時に肩回りの筋肉をほぐしてあげることが有効です。肩こり解消マッサージとしてご紹介したいのが、リンパの流れを刺激する方法です。
肩を大きく回して筋肉を温めたら、左右の鎖骨の窪みを5回ずつ指で擦りましょう。手指を肩の上部から鎖骨の方向に向かって動かしてあげると、リンパの流れが良くなります。
鎖骨のマッサージを終えたら、肩と首の付け根のあたりから円を描くように、肩の筋肉を外側へ擦ってください。
このリンパマッサージと組み合わせていただきたいのが、ダイナミックな動きを取り入れた動的ストレッチです。
肩幅に足を広げて立った姿勢から右手指で右の肩を、左手指で左肩に触れます。この姿勢から手指を肩から離すことなく、肘を大きく回しましょう。
30回以上回していると、肩を中心に身体がポカポカしてくるはずです。ストレッチというと筋肉を伸ばす体操や運動を思い浮かべがちですが、肩こりを改善するには肩の筋肉を伸び縮みさせるようなエクササイズも有効といえます。
肩こりに効くツボ
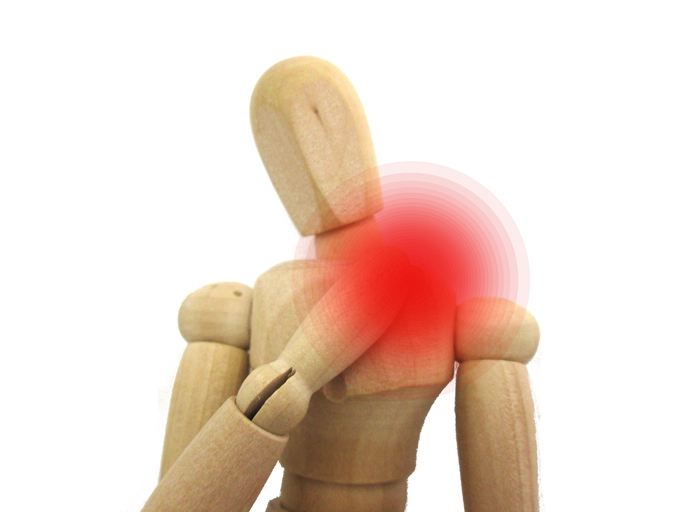 次に、「肩こりに効くツボ」を紹介していきましょう!
次に、「肩こりに効くツボ」を紹介していきましょう!
できれば、肩こりは自分で解消したいし、無くすことができたら、仕事の効率も高まりますよね。
肩こりに効くツボの場所や特徴、そして押し方を紹介していきます!
手三里(てさんり)
まず紹介するのは、「手三里(てさんり)」というツボです。
手三里は、肘の近くにあります。
探し方は、まず肘を曲げます。すると、肘の周辺に横方向にシワが出てきます。
その横ジワの奥から指3本分手前に位置しているのが、手三里です。
事務作業やエンジニアなど、パソコンを日常的に使う職業の人が酷使しやすい箇所です。
押すときの注意ポイントとしては、痛みが伴わない程度にそして気持ちいいと感じる程度に押してあげましょう。
風池(ふうち)
次に紹介するのは、「風池(ふうち)」というツボです!
風池は、首の近くにあるツボです。
具体的な位置は、2ヶ所あります。
まず、両手で耳の後ろを軽く押し、骨がある部分を確認しましょう。
それから、後頭部のちょうど真ん中にあるくぼみの位置を確認します。
後頭部のくぼみと、耳の後ろの骨の、ちょうど中間あたりに位置しているのが、風池です。
このツボも、デスクワークで事務作業やパソコン作業が多い方がよく使うため消耗します。
意識的にマッサージしてあげましょう。
肩外兪(けんがいゆ)
次に紹介するツボは、「肩外兪(けんがいゆ)」というツボです。
肩外兪は、肩甲骨の付近にあるツボです。肩甲挙筋という肩甲骨の、最も内側で、さらに最も上に位置しています。
肩甲骨の中で、最も首よりにあると言ってもいいでしょう。
肩こりの原因として、姿勢の悪さを挙げましたが、姿勢の悪さが原因の肩こりの場合、肩甲挙筋に過度な負荷がかかっているので、この肩外兪をマッサージしてあげることが、非常に効果があります。
中府(ちゅうふ)
最後に紹介する、肩こりに効果的なツボは「中府(ちゅうふ)」です。
中府は、鎖骨のあたりに位置しているツボです。
探し方は、まず鎖骨の下部を触っていき、出っ張りを見つけます。その出っ張った部分から、指一歩分上に位置しているのが、この中府です。
この中府も、デスクワークをはじめとする事務作業やパソコン作業の際は、ほぼ必ず使われます。
また、猫背の人もこの部分の筋肉がこわばることが多いので、猫背の人も意識的にほぐしてあげるようにしましょう。
肩こり改善に効果的な湿布
次に、肩こりの改善のために効果的な湿布について解説をしていきます。
そもそも、湿布は肩こりに効果があるのでしょうか?また、湿布には大きく分けて2種類あり、冷たい湿布と温かい湿布がありますが、どちらがより効果があるのでしょうか?
肩こりは、首回りや肩回りの筋肉がこわばり、緊張状態になってしまうことによって引き起こされるので、血行を促進し、緊張をほぐしてあげるような湿布が理想なので、その意味では冷湿布よりも温湿布のほうが効果的です。
温湿布は、血流の改善やリラックスにつながるからです。
局部を温めてあげることで、緊張状態や自律神経の乱れは解消に向かうので、体を冷やさないように温めることや、軽めの運動も同時に行うと、より効果的です。
>>肩こり対策に湿布は効果的?|湿布の種類や肩甲骨ストレッチも合わせて解説!
ひどい場合は早めに病院へ

肩こりは、慢性的でになっている人も多く、また悩んでいる人も多い普遍的な症状であるため、仕方がないと楽観視している人も多く見受けられますが、放置して悪化の一途を辿ると吐き気を伴うこともある見逃せない重大な問題です。
楽観視できるような軽い問題のまま抑えるためにもそして吐き気などの実害を及ぼさないためにももし、肩こりが酷くなり辛い場合はすぐに病院に行き、医師の診察を受けることをおすすめします。
合わせて読みたい!

鍼灸接骨院IWAMOTO 院長
岩本 玄次
Iwamoto Genji
人気コンテンツ
Popular Journals

開催中のキャンペーン一覧

ホッケー女子日本代表及川栞選手の睡眠に対するこだわり

卓球女子日本代表平野美宇選手にとってのリカバリーの重要性

睡眠不足が及ぼすさまざまな影響と質の良い睡眠|西多昌規(早稲田大学睡眠研究所所長)

住所やサイズが分からなくても贈れる「eギフト」について

睡眠の専門家に聞く、睡眠課題を解決する3つの方法|椎野俊秀(パラマウント ベッド睡眠研究所主幹研究員)

TENTIAL社員が選ぶおすすめ愛用アイテム

睡眠とまくらの関係について|田口直起(睡眠改善インストラクター)

リカバリーと睡眠のこだわり|稲垣祥(名古屋グランパスエイト)

商品開発担当者に聞く、リカバリーウェアBAKUNE開発ストーリー

ギフトレシート
その他の記事




