
肉離れのリハビリについて解説!ストレッチ・筋力トレーニングなど
この記事では、肉離れを起こした時の経過の見方や取り入れるおすすめのストレッチ・トレーニング方法を紹介していきます。
スポーツ中に肉離れを起こした後、筋肉痛などのケガとは違って、経過を見守るためにすべきことで分からないことも多いです。リハビリを行っていくためには、肉離れの状態をつかんでおくことが大切になり、中途半端な状態でストレッチなどの負荷を加えると、再発の危険も出てきます。
肉離れの痛みの程度にもよりますが、経過に合わせたケアとしてすべきことを解説していきます。
肉離れ予防のウォーミングアップ

スポーツ中の肉離れを未然に防ぐためのウォーミングアップ方法を3種類紹介します。何か特別なことが必要なのではなく、行うスポーツの前後に体のケアも含めて、肉離れの予防となるものばかりです。大きなケガにならないようにするために、ウォーミングアップをしっかり行う習慣を身につけていきましょう。
肉離れ直後は『RICE処置』

RICE処置という言葉に耳馴染みがない人が多いですが、肉離れが発症した直後にすべき処置方法になっています。
Rest(安静)・Ice(冷却)・Compression(圧迫)・Elevation(拳上)の4単語の頭文字を取った用語で、肉離れ直後に必要な応急処置を指しています。
痛まない姿勢で患部を休ませて、アイシングと同じ要領で患部の炎症を取り除くように冷やしていきます。そして圧迫することで出血や腫れを軽減できるように処置を行い、患部を心臓の位置より高く上げることで内出血や痛みを緩和していきます。
肉離れの場合は発症直後からRICE処置を行うことが鉄則とも言われており、最低でも1日から2日は安静と固定の処置を継続することが理想とされています。ただし、あくまで患部を悪化させない応急処置なので、RICE処置を行った後は必ず整形外科で受診するようにしましょう。
肉離れのリハビリについて

肉離れを一度起こした場合、同じ部位で再発することも多いため、しっかりとしたリハビリを行うことが必要とされます。ただし、肉離れを起こしてから経過した期間によってリハビリの質も変えていかないといけません。始めるタイミングや力の入れ具合などにも着目しながら紹介していきます。
肉離れ直後(急性期)
肉離れを起こしてすぐの急性期は、無理に動かさず安静にすることを第一に、アイシングで患部をしっかり冷やしながら弾性包帯で圧迫を行います。応急処置などを済ませた状態であったとしても、肉離れ直後の患部に激しい痛みや炎症を抱えた状態になるため、下手にストレッチやマッサージを行うのは、かえって患部を悪化させるので良くありません。特に、肉離れを起こしてから3日から5日の間は、無理にストレッチをして伸ばそうとしたり、筋トレをして筋肉に負荷を与えるようなことはせず、安静に保っておきます。
リハビリ開始の目安
しばらくの安静にして肉離れを起こした3日後くらいから、ハムストリングをストレッチすることで痛みがあるかどうかを確認します。太もも裏の筋肉であるハムストリングを伸ばすことで、患部の痛みや筋肉や筋が引きつるような感覚がなければ、リハビリを開始できる状況として判断されます。
確認方法としては、仰向けになって太もも裏を抱えるように脚を持ち上げて、膝をゆっくり伸ばしていきます。ハムストリングがしっかり伸ばされる姿勢になりますが、あくまでリハビリの開始を確認するために行うので、力任せに行ってはいけません。
リハビリでのストレッチ
肉離れから復帰していくためにストレッチからリハビリの段階を見極められます。けれども、患部に痛みがある場合は、無理に行うことで回復が遅れてしまうので安静第一になります。
肉離れを起こしてから3日位経過して痛みが治まってきたら、筋肉が軽く伸びる程度にゆっくりハムストリングのストレッチをしてみます。1回30秒で、3回から5回ほど行ってみて痛みを感じなければ、徐々に強度を上げていきます。痛みが残る場合は仕方がありませんが、安静にしている間に筋肉の機能は動かさないことで低下していきます。その上、動かさない時間が長くなるほど、筋肉に柔軟性が失われてしまうので、積極的に動かしていくようにします。ただし、痛みが残るのに中途半端な状態で行うと、肉離れを再発する危険があるので、状態を正確に見極めましょう。
リハビリでのトレーニング
肉離れから復帰していくためのリハビリで、無理なく行えるトレーニングを3種類紹介します。ある程度の負荷をかけたストレッチを行える具合まで回復してくると、肉離れを再発させないためにもトレーニングで筋力をつける必要が出てきます。あまりに強い負荷ではなく、体の様子を確かめながら実践してみましょう。
ヒップリフト
ヒップリフトは、仰向けになった姿勢でお尻の筋肉を使って上体を上げ下げすることで、ハムストリングの筋肉を鍛えるトレーニングになります。
マットの上などで仰向けになり、両脚は膝を立てるように構えて、両手はマットにつくようにしておきます。お尻を持ち上げた時に、肩・腰・膝が一直線になるようにして姿勢を30秒ほどキープしていきます。この時に、肉離れなどでケガをした後は、左右で筋肉バランスが崩れている可能性があるので、左右の筋力が均等になるまで継続することがポイントになってきます。
ヒップエクステンション
ヒップエクステンションは、うつ伏せ姿勢で脚を上げる動作でお尻から下半身の筋肉に刺激を与えるトレーニングになります。
マットの上でうつ伏せになり、両手は顔の前であごを支えるように置くことで、固定しやすくなります。脚は膝を曲げずに伸ばした状態で、腰から足先を持ち上げていきます。痛みを感じる手前、または骨盤が浮き始める手前まで持ち上げたら、ゆっくり脚を下ろしていきます。
脚を持ち上げる時は、膝が曲がらないようにして、太ももから足先を伸ばして行うことで、肉離れを起こした部位を少しずつ伸ばしていけるようになります。
ハーフスクワット
ハーフ・スクワットは、従来のスクワットとは違って浅めのスクワットであり、負荷を軽くしたリハビリに適したスクワットです。
両足を肩幅に開いて立ち、両手は腰のあたりに据えて、上体を少し前に倒して行います。方法は従来のスクワットのように膝が前に出ないように股関節を曲げていきますが、膝を45度くらい曲げたところまで下げたら、元の姿勢に戻ります。
負荷をかけずぎると肉離れを起こした部位が再発する場合もあるので、痛みが出ないように回数も制限しながら行うようにしましょう。
肉離れは再発しやすい
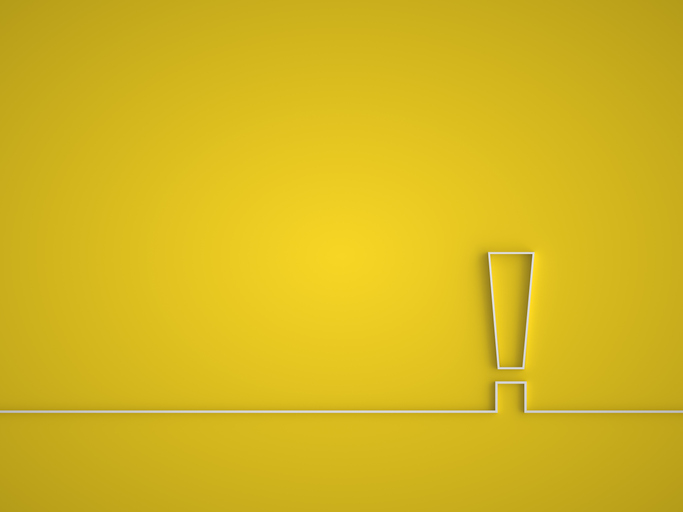
肉離れは一度起こすと、同じ部位または別の箇所を肉離れを起こすような再発が多いと言われています。肉離れの再発原因の一つに、筋肉を鍛えて筋力強化をしっかり行えていない状態で運動を行うことにあります。
肉離れで安静にしていたことで硬くなった筋肉を柔軟にするだけでなく、筋力もつけることを、肉離れを起こした時よりも強い状態にすることが理想とされています。
従来の運動のレベルでも問題なく体を動かせて、左右の筋肉バランスも保てるようになることで、肉離れ再発のリスクを抑えられるようになります。
まとめ
打撲や筋肉痛と違い、肉離れを起こすと無暗にストレッチをしたり、負荷をかけたりすることで完治の遅れや悪化を招きます。また、一度肉離れを起こすと再発する恐れも考慮しないといけないため、神経質になる人も少なくありません。ケガの程度にもよりますが、痛みなどの具合から状態を見極めて無理をしないところからストレッチを行っていきましょう。ただし、自己判断だけで肉離れの程度を見極めるのは難しいため、専門医に診察してもらい適切な処置を行ってもらうこともおすすめします。
最後に記事の内容をおさらい!
- リハビリを行うタイミングは肉離れの程度にも左右される
- 痛みが取れたらストレッチで徐々に筋肉に刺激を与える
- 柔軟性と筋力不足が肉離れの再発を引き起こす

TENTIAL編集部
TENTIAL Editorial Team
人気コンテンツ
Popular Journals

開催中のキャンペーン一覧

卓球女子日本代表平野美宇選手にとってのリカバリーの重要性

ホッケー女子日本代表及川栞選手の睡眠に対するこだわり

睡眠不足が及ぼすさまざまな影響と質の良い睡眠|西多昌規(早稲田大学睡眠研究所所長)

睡眠とまくらの関係について|田口直起(睡眠改善インストラクター)

商品開発担当者に聞く、リカバリーウェアBAKUNE開発ストーリー

住所やサイズが分からなくても贈れる「eギフト」について

睡眠の専門家に聞く、睡眠課題を解決する3つの方法|椎野俊秀(パラマウント ベッド睡眠研究所主幹研究員)

TENTIAL社員が選ぶおすすめ愛用アイテム

リカバリーと睡眠のこだわり|稲垣祥(名古屋グランパスエイト)

ギフトレシート
その他の記事



