
シンスプリントとは。原因、症状、治療、再発予防ストレッチを紹介
スポーツをしている最中に脛の内側が痛くなってきた人はシンスプリントが発症している可能性を考慮しましょう。
シンスプリントはオーバーワークによる過度な負荷が原因で脛を構成する骨にある骨膜で炎症が起きている症状です。
こちらの記事ではシンスプリントの原因や症状、治療についてそれぞれ項目を設けたうえで詳しく解説していきます。
シンスプリントを再発させないために取り組むべきトレッチも紹介するので、シンスプリントに関する理解を深めたい人は参考にしてください。
シンスプリントとは
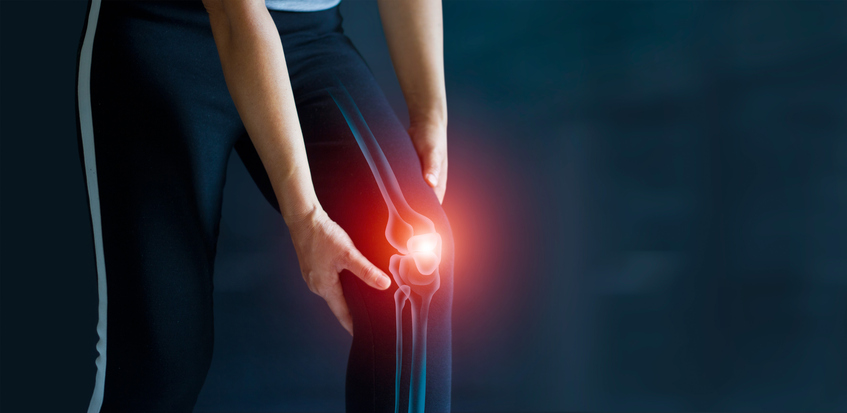
シンスプリントとはスポーツをしている人によく見られるケガの一種であり、脛の内側に痛みを感じる症状です。日本語では脛骨過労性骨膜炎と表記することもあります。脛全体の下から3分の1程度のエリアが痛むことがほとんどです。
シンスプリントはスポーツ中の動作の中でも、跳躍や急停止をはじめとした脛に負担がかかる動作によって引き起こされます。初期段階であれば運動したときにだけ痛みを感じるに留まりますが、進行するとスポーツをするのが難しくなるほどの痛みに発展する点に注意しましょう。
シンスプリントは骨膜における炎症が生じる症例です。また、よく似ている症状としては疲労骨折が挙げられます。実際、シンスプリントと疲労骨折の初期段階はよく似ているため、診断結果がシンスプリントから疲労骨折に変更されるケースもあることを覚えておきましょう。
治療については安静措置で痛みを取り除くほか、炎症を抑制する薬を活用することもあります。痛みが引いてからはストレッチやトレーニングを取り入れて、競技復帰に向けて準備を進めていくのが一般的です。
シンスプリントの原因

シンスプリントが発症した人の多くは練習のし過ぎ、いわゆるオーバーワークの傾向にあります。シンスプリントで痛みを感じる脛の内側の筋肉は跳躍や走行、急停止といった運動の際に負荷がかかる部位です。
激しい運動によって、脛を構成する筋肉と骨を繋ぐ骨膜と呼ばれる部分が何度も引っ張られ、炎症を起こしてしまうのがシンスプリント発症の理由です。
小学生や中学生といった筋肉が充分に備わっていない世代の人が激しい運動をすると、筋肉による衝撃吸収効果が発揮されないまま、脛の骨に負荷がかかるというわけです。
また、成人している人でも筋肉の柔軟性が足りていないと筋肉の衝撃吸収効果が働かず、シンスプリントに悩まされることもあります。
シンスプリントの症状

シンスプリントの人の脛の筋肉や骨の特徴として、筋肉が疲労しているケースがよく見られます。オーバーワークによって筋肉を酷使しながら、必要なケアが行われなかったせいで筋肉に疲労が溜まっているのです。
疲労が蓄積した筋肉が硬さを帯びて、本来備わっている衝撃吸収能力が活かされることがなくなります。その結果、ヒラメ筋をはじめとした脛を構成する筋肉と骨を繋ぐ骨膜に炎症が生じ、痛みを感じてしまうというわけです。
運動中にだけ痛みを感じる場合は初期のシンスプリントに分類されます。そこから徐々に痛みが悪化すると、日常生活に思想を来すほどの痛みに発展するのがシンスプリントの特徴です。
下肢を酷使するスポーツに取り組んでいる人の中でも、シンスプリントはランナーにおいてよく見られます。
>>シンスプリントの症状について|シンスプリントの症状レベルも解説!
シンスプリントの治療とリハビリ

シンスプリントはスポーツに取り組んでいる人に見られる症状です。そのため、単に痛みを取り除くだけでなく、競技への復帰を前提に治療を進めていきます。
シンスプリントは疲労骨折の初期症状とよく似ていることから、レントゲンや超音波画像診断、MRIといった方法で両者を区別するのが治療における最初の一歩です。
シンスプリントと判断した場合、まずは運動量を制限することから始めます。
強い痛みを感じている段階では、シンスプリントの原因となり得るランニングを休止するのが基本です。炎症を抑制するための措置としてアイシングを実施するほか、炎症を抑える薬を用いることもあります。
痛みが引いてきたら、下肢のストレッチングを含む運動を徐々に取り入れて、競技復帰までの道のりを歩んでいくのがシンスプリント治療のリハビリです。動けるようになったからといって自己判断で練習量を増やすのではなく、医師の診断に従いましょう。
ストレッチ方法
 シンスプリントは脛周辺の筋肉を酷使した結果、疲労の蓄積や筋肉の柔軟性の欠如といった要因が重なり、脛の内側に痛みが生じる症状です。
シンスプリントは脛周辺の筋肉を酷使した結果、疲労の蓄積や筋肉の柔軟性の欠如といった要因が重なり、脛の内側に痛みが生じる症状です。
これを予防、改善するにはストレッチで筋肉を柔らかくしたうえで、疲労を取り除きましょう。
シンスプリント対策として実施したい3つのストレッチを紹介します。
- 腓腹筋のストレッチ
- 後脛骨筋のストレッチ
- ヒラメ筋のストレッチ
腓腹筋のストレッチ
脛周辺の筋肉の中でも、ふくらはぎの表面を構成するのが腓腹筋です。シンスプリント対策のストレッチを実施するうえでも、腓腹筋は重点的に伸ばすべき部位といえます。
ストレッチの最初の手順は壁と正対した状態で脚を前後に開くことです。この状態で壁に手を着いたら、後ろに出した脚のアキレス腱を伸ばすイメージで、壁に体重を乗せましょう。筋肉が伸びた状態で15秒キープします。
壁に体重を乗せるだけでなく、後ろの脚をしっかり伸ばすのがポイントです。
後脛骨筋のストレッチ
後脛骨筋とは脛周辺の筋肉の中でもいわゆるインナーマッスルに分類されます。外側からは見えにくい一方、脛を構成する骨と深く結びついているため、ここをストレッチすることがシンスプリントの予防や改善に繋がる重要な部位です。
後脛骨筋を伸ばすには、脚を前後に開いて前に体重をかける運動を行います。このとき注意したいのは、後ろ側の足裏全体を地面に密着させることです。
また、後ろの爪先を内側に向けることで、ストレッチ効果が高まります。筋肉が伸びた状態を感じたら、15秒程度キープしてください。
ヒラメ筋のストレッチ
ヒラメ筋もまた、脛周辺の筋肉を構成する要素のひとつです。腓腹筋の下側にある筋肉であり、ヒラメ筋の強張りが脛全体の柔軟性を左右することもあります。ヒラメ筋を伸ばすストレッチの基本姿勢も脚を前後に開いた姿勢です。
後ろに置いた側の足裏を地面から離すことなく、真下に向かって体重をかけましょう。
アキレス腱を伸ばすときのように体重を前にかけるとヒラメ筋を上手く伸ばすことができないので注意してください。
背筋に線を通した状態のまま、後ろの膝を地面に近づけるイメージで取り組みましょう。
こちらも筋肉が伸びた状態を15秒キープします。
>>シンスプリントのストレッチ方法について解説|予防と痛みの緩和に効果的
シンスプリントとインソールの効果

シンスプリントの予防や改善に努めたいと考えている人は自分が今使っているインソールを見直すことから始めてみましょう。なぜなら、インソールの中にはシンスプリントから下肢を守る効果が備わっているものもあるからです。
具体的には足裏のアーチを維持する機能が付いているものを選んでください。
アーチサポート機能は足裏が本来持つアーチを底上げします。足裏のアーチは着地や踏み切りにおける衝撃を吸収してくれることから、脛周辺の骨や筋肉にかかる負荷を軽減し、シンスプリントを防ぐことに繋がります。
また、足裏のアーチが持つ衝撃吸収機能は下肢に疲労が蓄積するのを抑制することにも繋がるため、疲労によってランニングやジャンプのフォームが崩れ、シンスプリントが発症してしまう事態を予防することが可能です。
足裏のアーチが崩れている人はアーチサポート機能が備わったインソールを試してみましょう。
テーピング・サポーターの効果

シンスプリントからの回復を促したい場合やシンスプリントを予防する手段としてサポーターやテーピングを用いるケースも見受けられます。ふくらはぎや脛をすっぽりと覆う形状がシンスプリント対策として活用されるサポーターの特徴です。
サポーターを選択する際には締め付けの強さだけでなく伸縮性や通気性、発汗性といった点にもこだわりましょう。シンスプリント対策としてテーピングを使用する場合は血流を阻害しないように注意してください。
基本的にはキネシオテープと呼ばれる柔らかいタイプのテープを活用します。脛の前側の筋肉が硬くなっているときは爪先を伸ばしたときに強張る筋肉の外側にテープを貼りましょう。
動きを制限したいからといって強く締め付けてしまうと血行が悪化して回復が遅れることもあるので注意してください。
まとめ
シンスプリントに関する概要をまとめた今回の記事は以下の3点に集約できます。
- シンスプリントは脛の内側に痛みを感じる症状であり、スポーツをしている人によく見られます。
- 走行や跳躍、急停止といった動作を繰り返すうちに、脛を構成する骨にある骨膜が炎症を起こすことがシンスプリント発症のメカニズムです。
- シンスプリントの予防や改善にはストレッチが役立ちます。腓腹筋や後脛骨筋、ヒラメ筋といった筋肉を重点的に伸ばしましょう。
合わせて読みたい!
人気コンテンツ
Popular Journals

TENTIALのリカバリーウェアの選びかた

開催中のキャンペーン一覧

ホッケー女子日本代表及川栞選手の睡眠に対するこだわり

BAKUNEシリーズラインナップ

卓球女子日本代表平野美宇選手にとってのリカバリーの重要性

睡眠不足が及ぼすさまざまな影響と質の良い睡眠|西多昌規(早稲田大学睡眠研究所所長)

住所やサイズが分からなくても贈れる「eギフト」について

睡眠の専門家に聞く、睡眠課題を解決する3つの方法|椎野俊秀(パラマウント ベッド睡眠研究所主幹研究員)

TENTIAL社員が選ぶおすすめ愛用アイテム

睡眠とまくらの関係について|田口直起(睡眠改善インストラクター)

リカバリーと睡眠のこだわり|稲垣祥(名古屋グランパスエイト)

商品開発担当者に聞く、リカバリーウェアBAKUNE開発ストーリー
その他の記事




